吟剣詩舞 和 翔 流 へようこそ 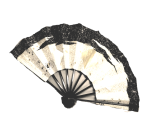
【 便利なリンク 】
剣詩舞は 剣舞 と 詩舞 の総称で、剣舞は日本刀を、
詩舞は扇子で紋付袴を着て詩吟の情景や心情を舞で表現。
詳しくはバナーを クリック しますと リンク 先が開きます。
![]()
おかげさまで当社は今年35周年を迎えることができました。これまで当社を支えて下さいましたお客様、保険会社関係者の皆様、社員のお陰であり感謝申し上げます。
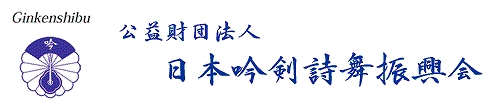
日本吟剣詩舞振興会は、日本の伝統芸道である吟詠・剣舞・詩舞の振興を目的とする公益法人として、昭和43年(1968年)10月に全国の吟剣詩舞に親しむ人たちの総本山として文部科学大臣の許可を受けて設立された。
平成25年(2013年)4月には内閣総理大臣より公益認定を受け、公益財団法人 日本吟剣詩舞振興会となり、新たな歴史を刻み続けている。
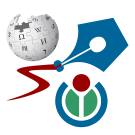
剣詩舞(けんしぶ)とは、広い意味では、刀剣を持って舞うこと。本来は、特に詩吟に合わせて日本刀を抜いて舞うことを指す。剣舞(けんぶ)とも。起源としては、武士から起こったものである。明治初期に日比野雷風(神刀流開祖)が剣術の形(型)を取り入れて現在の形に整理した。
吟と舞は、基本的に別々の者が行う。人数は決まっておらず、吟者と舞者が一対一の場合もあれば、吟者一人に対して複数人で舞う場合も多い。吟者の格好は決まっていないが、舞者は袴に白襷、白鉢巻の支度で舞い、詩の情緒を表現する。演目によっては、刀に加えて扇子を用いることもある。
また、詩吟に合わせて扇子のみを持って舞うことは扇舞(せんぶ)または詩舞(しまい)という。剣舞と扇舞を合わせて 剣扇舞 (けんせんぶ)と呼ぶこともある。

相撲甚句(すもうじんく)とは、歌詞は7、7、7、5の甚句形式です。
土俵上で力士5〜7人が輪になって立ち、輪の中央に1人が出て独唱する。周囲の力士たちは手拍子と『どすこい』、『ほい』、『あ〜どすこいどすこい』といったような合いの手を入れます。
私たちは、古来から受け継がれる伝統・文化を大切にする思いから、その文化を継承していきたいと思っています。
Copyright © 2024 吟剣詩舞 和翔流 宗家 前野 翔漱(和子) All Rights Reserved. 北海道滝川市西町2丁目4番28号 有限会社 前野保険事務所 0125-23-0556